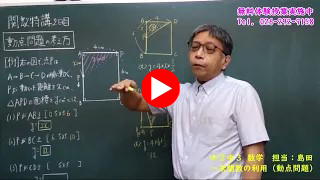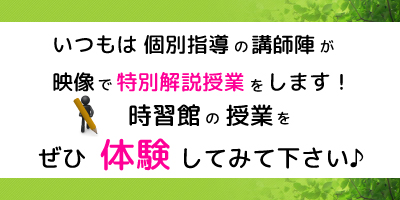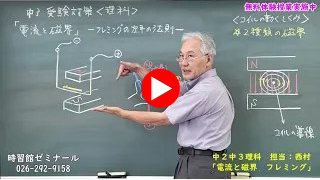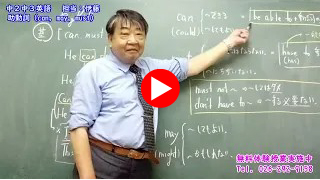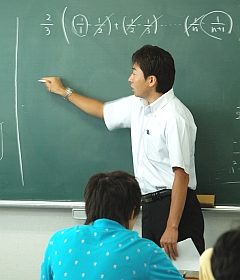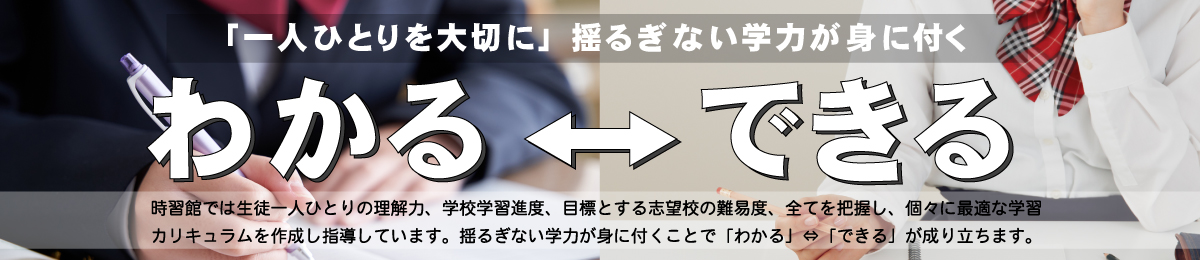


お問い合わせは コチラ!
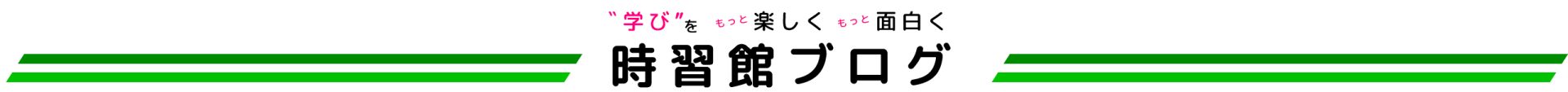

高校化学 物質量計算
高校化学で多くの高校生が最初に苦労する計算が
物質量計算
物質量の単位は「mol」を使います
例えば、
鉛筆12本=1ダース
卵10個=1パック
など、ある特定のまとまりにしたものを「ダース」や「パック」として扱いますが
高校化学でも同じように特定のまとまりを作ったものを「mol」という単位で扱います
そのまとまりの個数は「アボガドロ定数」とも呼ばれており
6.0×1023個のまとまりを「1mol(モル)」として定義していきます
さて、ここからが少し面倒で
「g(質量)」から「L(体積)」への変換や、
「L(体積)」から「個数」への変換など、
必ずこの「mol」を経由して変換していくことになります
そこで、次の3パターンの計算式はぜひ覚えておきたいものになります
【パターン①】 g(質量)からmolを求める
mol = g(質量)÷ 分子量(原子量)
【パターン②】 L(体積)からmolを求める
mol = L(体積) ÷ 22.4
【パターン③】 個数からmolを求める
mol = 個数 ÷ 6.0×1023
これらの使い分けは、問題文の中にある数値情報をもとに
①~③のどの計算式を利用するか判断すれば良いです

高校生 夏期講習 数学特別講座
高校生夏期講習の数学特別講座(ⅠA/ⅡBC)が終了しました
今回の数学特別講座では受験に向けた基礎確認や今後の学習方針を説明しつつ
ⅠAでは、主に「共通テスト」類題を利用しながら
教科書等には載っていない重要公式や途中式の組立方、計算工夫を解説し
ⅡBCでは、複数の単元の知識や公式を同時利用していく複合問題を扱いました
ちなみに微分積分単元の問題では、面積を求める問題が
必ずと言っていいほど出題されますが
ここで覚えておきたい面積公式がいくつかあります
例えば、曲線と直線で囲まれた面積は出題頻度も高く
下のような公式はぜひとも覚えておきたいものとなります


また授業内では現役生が間違いやすい点や、見落としてしまう点なども
解答解説時にアドバイスしていったので、
その点を今後の各自の受験勉強にも役立ててもらいたいと思います
例えば、「問題文先頭に記入してある条件式の見落とし」は
現役生に多くみられるケアレスミスのうちの一つです
高校生 夏期講習スタート
7月21日(月)本日から高校生の夏期講習が開始されました本日の夏期講習で行ったのは3講座 ●高3個別講座 北海道大学や新潟大学などの入試過去問や数学Ⅲの微分公式確認、 三角関数の諸公式を利用した最大最小問題など扱いました […]
高校化学 「分子量」と「式量」
高校化学の学習初期に 原子量分子量式量 という用語が出てきます 原子量とは、簡潔に言えばある一定のまとまりを作った時の重さのことですなお、原子量は問題文等に記入してあるので特に覚える必要はありませんが、代表的なものだけ覚 […]
長野県入試 平均点発表
先月、長野県教育委員会から令和7年度長野県後期選抜の平均点が発表になりました。この結果の講評と来年度入試の展望について説明したいと思います。 入試易化。久々の平均300超え 本年度入試はすべての科目で前年を平均が上回る易 […]