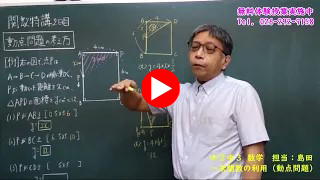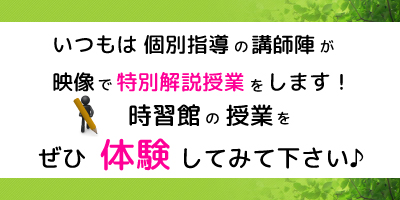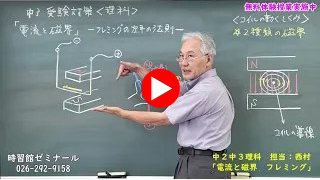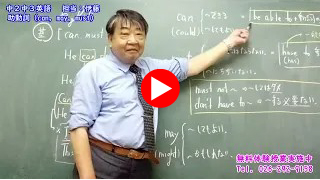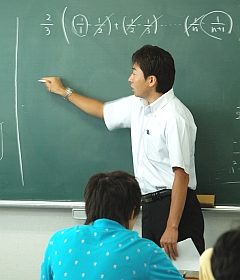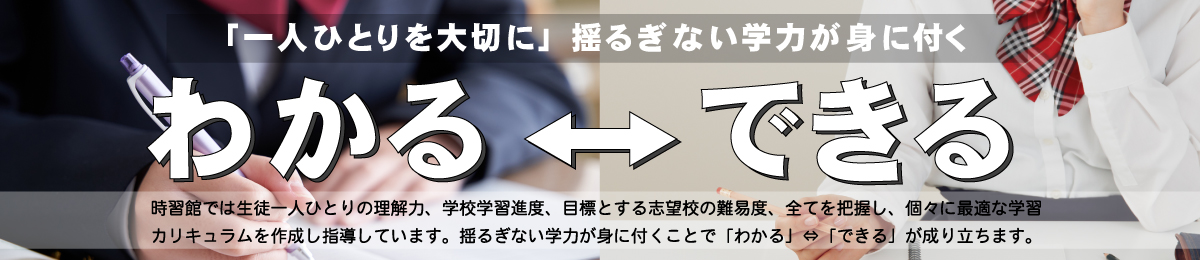


お問い合わせは コチラ!
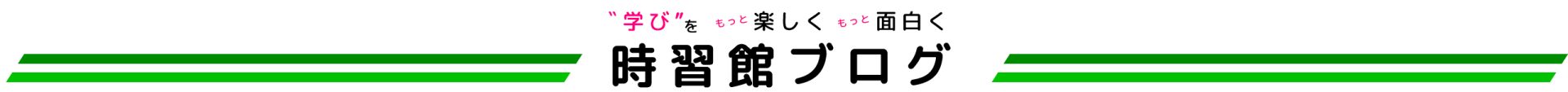

星に願いを
6月がそろそろ終わり
もうじき7月ですが
7月言えば
七 夕
七夕伝説で有名な星座が
こと座の1等星ベガ(織姫星)と、
わし座の1等星アルタイル(彦星)です
この2つの星は天の川を挟んで輝いていています
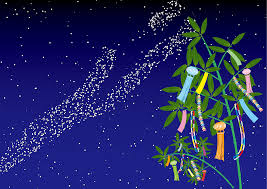
ところで恒星の明るさを表示するときに使うのが
「~等星」という表示方法ですが
古代ギリシャ人のヒッパルコスは
次のように恒星の明るさを分けました
肉眼で見える最も明るい恒星を「1等星」
もっとも暗い恒星を「6等星」とし、
その間を5等級に分けました

一般に、m等星、n等星の恒星の見かけの明るさを
それぞれ「Lm」「Ln」とおくと
m等星とn等星の明るさの比は、
次の等式で表されることが証明されています
Lm / Ln = 100 (n-m) / 5
この両辺を底が10である常用対数を利用して、変形していくことで
Lm - Ln = -2.5 log10(Lm/Ln)
という式になります
常用対数は、高校2年生の「数学Ⅱ」で学習していく内容で
学校でもこの単元を扱うときに星座間の距離や星の輝きの話題が出るかもしれません
なお、この式から1等級違うと
星の輝きが 2.5倍 変わるということが分かってきますが
もう少しわかりやすい数字で表すと
5等級違ければ、約100倍明るさが異なります
ちなみに恒星とは太陽のように自ら輝く星のことで
代表的な恒星は、ベガやアルタイルの他に
おおいぬ座の「シリウス」
オリオン座の「ベテルギウス」
おうし座の「アルデバラン」
さそり座の「アンタレス」
おとめ座の「スピカ」
はくちょう座の「デネブ」
こぐま座の「ポラリス」
こいぬ座の「プロキオン」
など、多数あります
(それこそ星の数ほど)
ちなみに「等級」には実は2種類の表示方法があり
見かけの等級
絶対等級
とあります
地球から見ると、太陽が最も輝いており眩しい眩しい!
でも、これは太陽が宇宙で一番明るく輝いているわけではありません
たまたま地球との距離が近いためです
そのため、恒星本来の明るさを比較しようと思ったら
全ての恒星を同じ距離に並べて、その明るさを比較する必要があります
この、すべての距離を等しく(10パーセクの距離)して
比較した等級のことを「絶対等級」と呼びます
10パーセクとは、「32.6光年」の距離になります
もうじき七夕
勉強に疲れたら
夜空を見上げ、星の輝きを見て
少しだけ頭を休ませてみてもいいかもしれません

信州大学工学部 学科改編

信州大学工学部が新年度入試から学科が再編成されます
現在、信州大学工学部は
「物質科学科」
「水環境・土木工学科」
「建築学科」
「電子情報システム工学科」
「機械システム工学科」
の全5学科に分かれていますが、新年度からは
「先鋭融合コース」
「応用化学コース」
「環境・エネルギー材料コース」
「水環境・土木コース」
「電気電子コース」
「機械物理コース」
「知能機械コース」
「建築学コース」
「情報サイエンスコース」
「情報デザインコース」
の全10コースに細分化される予定です
先鋭融合コースのみ募集人数が20名で、他のコースは50名前後が募集人数になります
このうち、「先鋭融合コース」だけ他のコースとは異なり、
入学後に学習したい専門分野を決めていくことになります
また、受験に関しても「先鋭融合コース」は、
いわゆる国立2次試験と呼ばれる「選抜入試(前期・後期)」がなく、
募集人数20名のうち、約7割にあたる13名を
「総合型選抜入試」で募集していきます
「総合型選抜入試」では、
①学校評定
②志望理由書
③自己推薦書
④小論文
⑤口頭試問を含む面接
で合否が決まります
出願は、「9月下旬」で受験は「10月下旬」、合格発表が11月上旬と
かなり早い時期に合否が決まります
信州大学工学部の受験を検討している受験生は、学科が変わる点や入試方法の相違点など
いくつか留意点があるため、信大工学部のホームページから詳細確認をしておいた方が良いでしょう
「鉄道」金を失う!?
【問題】「ひがしにほんりょかくてつどう」を漢字で書きなさい ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー鉄道にはいろいろな「マニア」が存在していて有名なのは、乗ることを愉しむ「乗り鉄」車両の撮影を愉しむ「撮り鉄」など中には […]
高校1年生 夏期講習
暑い日が続き、梅雨を知らずに夏を迎えそうな勢いです学校テストも近いので、自習に来る生徒も多いですが、熱中症に注意し、こまめに水分補給しながら学習に励んでもらいたいものです さて、7月下旬から時習館でも夏期講習が始まります […]
中学社会 やはり暗記は大事?
「社会科は暗記科目」という印象を持っている人も多いと思います。しかし近年、長野県公立入試においては(全国の公立入試においても)いわゆる単純暗記では解けないタイプの問題=思考力・記述力タイプの問題が増えてきています。では、 […]