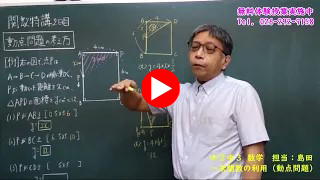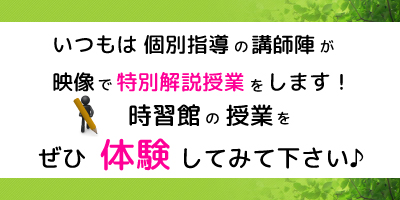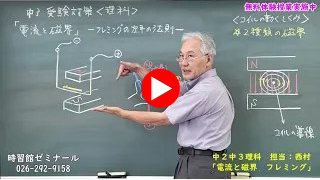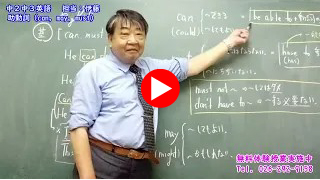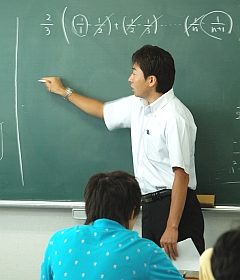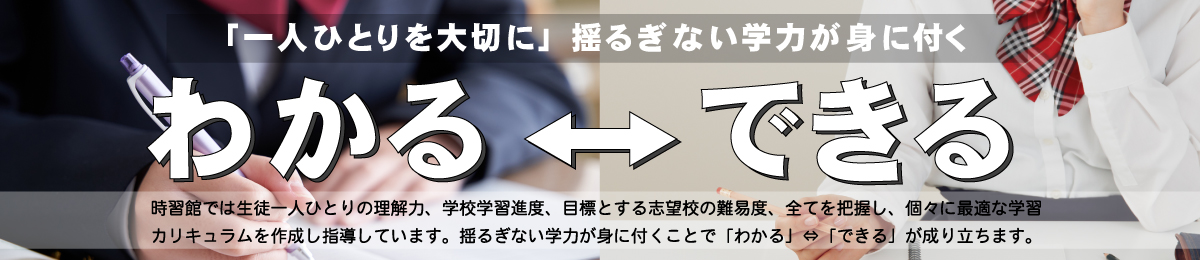


お問い合わせは コチラ!
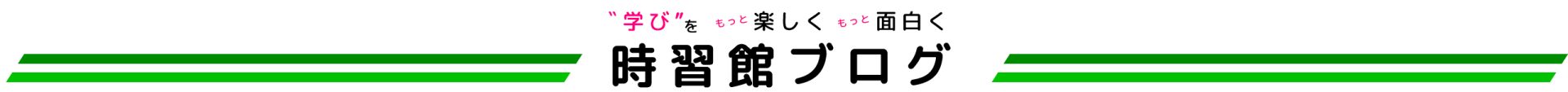

大学入試 共通テスト
1/17(土)+18(日)に「大学入試共通テスト」が実施されました
塾生たちも「緊張+入試の重圧」に打ち勝って受験してきてくれたかと思います
今年の共通テストの問題は、大学入試センターのホームページから閲覧できます
大学入試センターHP
→ https://www.dnc.ac.jp/kyotsu/shiken_jouhou/r8/r8_honsiken_seikai.html
共通テスト後の予定(国立大学志願者)は、
【出願受付】 1/26 (月)~ 2/4日(水)
【前期試験】 2/25(水)+26(木)
【合格発表】 3/6(金)~3/10(火)
【入学手続き締め切り】 3/15(日)
【後期試験】 3/12(木)以降
【合格発表】 3/20(金)~3/24(火)
【入学手続き締め切り】 3/27(金)
となりますが、今週末からは私立大学の一般入試も始まるため
受験生にとっては2月下旬ごろまではまだまだ気が抜けない戦いが続きます
大学入試 共通テスト
2026年が始まりました
新年早々、高校3年生の受験生たちにとって大きな行事があります
大学入試共通テスト
1/17(土)18(日)の2日間行われ
国公立大学志願者にとっては、1次試験にあたるものとなります
試験終了後に自己採点をした後、その結果をもとにどの大学に出願していくか決め、
2/25、2/26の両日もしくは1日の2次試験へと進んでいきます
共通テストがマーク形式試験に対して
2次試験は完全記述形式の試験になるため
共通テスト後の受験勉強では記述形式の解答作成をメインに据えた学習に切り替わります
週の初めに大雪になり少し心配ではありましたが、
共通テスト当日は天気も良さそうで交通の乱れもどうやら無さそうです
受験生にとっては最初の第一関門と呼べる入試まで
残すところあと1週間を切りましたが
体調管理とともに、食事にも注意して
受験勉強を頑張ってもらいたいと思います